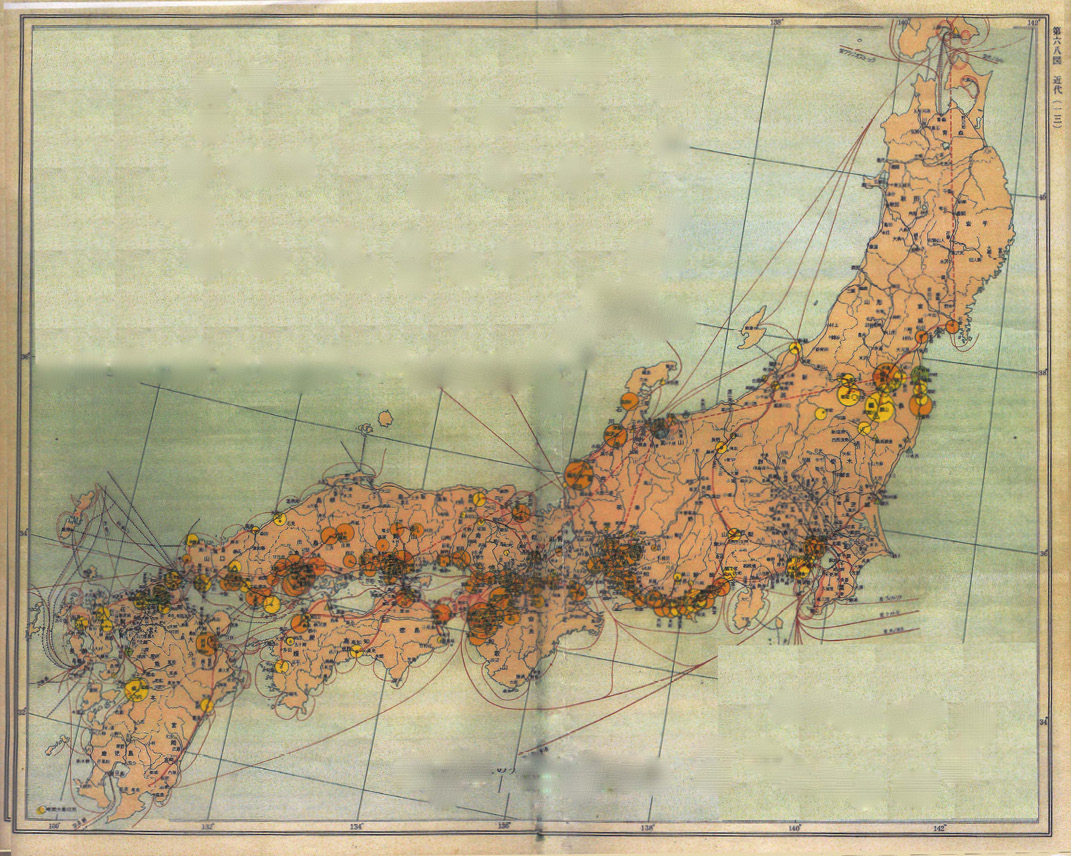さて、何から始めよう。
まず導入は、昔話から。
今から10年前、いや、もう少し前だったかもしれない。
私は年の近いある活動家と議論をしていた。仮にAとしよう。Aは知恵も度胸もあるアナキストで、酒好きで、集団を統率する力のある活動家だった。
Aと議論をしたのは、運動体の基軸を何におくかである。私が主張したのは、運動集団というものはどうあがいても私党であるということ、そして、我々は私党でよいのだということだった。それは経験的な事実から、そうだった。人間が運動集団を形成するとき、それは何か公的なお題目にぼんやりと結集するのではなくて、個別具体的な人間が個別具体的な人間についていくのである。そういう集団は、どこをどう転んでも私党である。
それに対してAは、運動体が私党であるという事実を認めつつ、私党ではないものにむかって、公的な形式を備えるべきである、と主張した。私党というのは集団の起源としてはあるとしても、それは過渡的な段階とみなすべきであろうということだ。我々の集団のもつ私党的性格は、徐々に払拭されていくべきである、と。ある意味、常識的な主張だ。
私はAにむかって「公的な形式だなんて、そんなゴマカシはできないよ」と言ったが、一方で迷いもあった。私は、私党を私党としてやりきることに絶対的な自信をもっているわけではなかった。公的な形式を備えた団体というものに、半信半疑ながら少しだけ魅かれ、期待しているところもあったのだ。Aの考える組織論は、もしかしたらうまくいくのかもしれない、と。
また、集団に公的な形式を与えることは、実践的な要請としてもあった。集団が労働組合としての交渉権を確立するには、規約を作り、代表を選出し、監査役をおかなければならない。そういう公的な形式を便宜的にでも整えておかなければ、合法的な「労働組合」にはならない。もしもそうした形式を整えなかったら、我々の争議行為はすぐに刑事事件にされてしまう。
この私党をめぐる議論は、議論というほどの時間もとらず、それっきりになった。双方とも結論に強い確信を持っているわけではなかったからだ。この問題について結論が出ないまま、Aはある労働組合の中核メンバーを担い、私は「海賊研究会」を主宰して私党の構成原理を考えるようになった。
あの議論から10年たって、結論が出たわけではないけれども、学ぶべき経験はいくらか積んだと思う。もういちど、集団の基軸とするべきものについて、「私的なもの」と「公的なもの」について述べたいと思う。
* * *
私は今も「公的なもの」に疑いをもっている。疑いというよりももっと強い、あれは、罠だな。「公的なもの」の罠。パラドックスと言ってもいい。
まず、「公的なもの」のなかでももっとも大きく、もっとも「公的」だと信じられている組織から考えてみよう。警察について。
W・ベンヤミンが『暴力批判論』のなかで指摘したのは次の事実である。
警察官は法を遵守し、たんに法を運用しているだけだと考えられているが、実際にはそうではない。警察官はどういう場面でどういう法を適用するべきかを決定している。現場にいる末端の警察官が、法を解釈し、運用を決定している。遵守されるべき法は、日々、現場の警察官によって解釈替えされ、作り変えられているのである、と。
同じことをG・ドゥルーズも言っている。「重要なのは法ではなく、判例である」と。
このことは、実際に警察と対峙したことのある人なら経験的に知っていることだ。法は、場面によって運用されなかったり、反対に拡大解釈をして運用されたりする。
「公的なもの」の頂点にある法は、警察やなんらかの政治勢力によって私物化されうるものである。そして、そうした警察力の私的な運用が可能になっているのは、法が「公的なもの」と信じられ、警察・検察が「公的なもの」を遵守していると信じられているからである。多くの人は信じている。法治国家において警察がそうそう間違えるはずがない、と。そうかもしれない。ところで、その根拠は? 法の運用の妥当性を担保するものは? 裁判所? 制度としてはそのとおり。しかし実態としては、裁判所の判事が検事に従属する場面がたびたびあるのである。そんなことはあってはならないことだ。制度としても道理としても、判事が警察・検察の顔色をうかがうなんてことは、あってはならないことだ。そしてそのように信じられていることによって、警察の横暴は見逃され、正当化されるのである。われわれは「公的なもの」をかたく信じることによって、権力の私物化=私物化された暴力を直視することができなくなってしまうのである。
問題は「官僚制」なのか? そうかもしれない。しかし私はもう一歩踏み込んで、私たち自身が信じている「公的なもの」という想念について、俎上にあげるべきだと思うのだ。
* * *
「公的なもの」の罠について、こんどはもっとも小さな場面を考えてみよう。
ドメスティック・バイオレンス(親密な暴力)について。
ドメスティック・バイオレンスは、一時的で偶発的な暴力のことではない。それは持続的な構造に支えられた暴力である。ドメスティック・バイオレンスを支える構造とは何か。そのカギを握っているのは、加害者でも被害者でもなく、第三者である。この暴力を持続させる構造は、当事者ではない第三者が、ある暴力を容認するか容認しないかにかかっている。
夫婦または恋人というのは、たいてい共通の友人がある。あなたがその友人だったとしよう。ある日、女性から暴力の被害にあっているという相談を受けたとしよう。あなたはおそらく、女性と男性の双方から事情を聞こうとするだろう。あるいは、双方をよく知る人物をとおして、二人の間に何があったかを知ろうとするだろう。つまり二人の仲裁者として、問題の解決策を探ることになる。
ここで仲裁者が直面するのは、双方の供述が示すハレーションである。加害者と被害者の供述は、はっきりとした対照を示すことになる。
加害者の供述は、理路整然としている。話に整合性があって、一貫性がある。
それに対して被害者の供述は、混乱している。話に一貫性がなく、つじつまのあわないことばかりを言う。彼女は、自分がどうしていきたいのか、まったく明確でないのだ。
あなたは仲裁者として、どちらの話を信じるだろうか。理路整然とした加害者の話か、混乱した被害者の話か。
このことを言い換えれば、加害者の供述とは、「公的」に通用するだけの充分な整合性を備えた供述である。第三者がそれを聞いて、さらに別の第三者に話すときに、苦も無く伝えられる形式を備えている。
それにたいして被害者の供述は、一貫性がなく矛盾を含んでいて、第三者が別の第三者に伝達することが難しいものである。
ここであなたが理路整然とした話を信じるなら、それは、ドメスティック・バイオレンスを持続させる構造を維持・強化してしまうことになる。ここであなたが信じるべきは、「混乱した女」の話である。
なぜか。なぜならドメスティック・バイオレンスとは、そもそも分裂し矛盾した出来事だからである。お互いに愛しあい慈しみあうべき夫婦または恋人の間で、暴力が生まれているのである。ドメスティック・バイオレンスとはそうした「矛盾した」現実なのである。だから、被害者の供述が分裂し二転三転するのは当然のことだ。被害者が別れたいと言い、別れたくないと言い、自分がどうしたいのかがまったく定まらない、このことは、ドメスティック・バイオレンスという出来事の全体を彼女がもれなく認識しているからである。他方で、加害者の供述が、分裂も矛盾もなく整合的であるのは、彼が生起している現実の全体を認識していないからである。加害者は、現実のある重要な要素を認識しないことによって、矛盾のない整合的なストーリーを形成することができるのである。
繰り返しになるが、ドメスティック・バイオレンスとは構造化された暴力であって、この構造のカギを握っているのは、当事者ではない第三者たちである。当事者双方から事情を聴いた第三者たちが、何を信じるかが、問題の核心である。ドメスティック・バイオレンスに直面した第三者が本当に問題を解決させようとするならば、混乱し分裂した供述者にこそ耳を傾けなければならない。
ここにあるパラドックスとは、「私的な暴力」が、「公的なもの」を信じようとする人々によって、維持・強化されてしまうというパラドックスである。第三者の誰もが問題解決を望んでいる。しかし、第三者が「私的な暴力」を解消させようとするときに、彼らの「公的なもの」をめぐる信念は役に立たないし、かえって暴力を保存することに役立ってしまうのである。
ドメスティック・バイオレンスという概念から引き出すべき論点は、ここである。これはジェンダーの問題であるという以上に、暴力をめぐる問題である。ある暴力が、どのように第三者に容認され、維持・強化されるかという、構造の問題だ。私がここで注意を喚起したいのは、「私的な」暴力と、「公的なもの」をめぐる信念とが、意外にも密接であるということだ。
ドメスティック・バイオレンスの加害者は、とたんに饒舌になる。まるで弁護士になったかのように、理路整然と経緯の説明をはじめる。彼が、他の事柄でたんに釈明を求められているというだけなら、ここまで饒舌になることはない。仕事が遅いとか、酒を飲み過ぎだとか、肥満をどうにかしろとかいうことで責められているのなら、彼は饒舌ではなくむしろ寡黙になっていくだろう。彼が理路整然と、ときには「公正さ」を示しながら、冷静に話すことができるのは、これが暴力をめぐる問題だからである。
だがこれは、「公的なもの」という想念の起源を考えれば、あたりまえのことである。そもそも私的である権力の支配が、自らを正当化するためにまとった衣が、「公的なもの」という想念なのだから。それははじめから、人々が暴力を容認したり見なかったふりをしたりするための機制を備えているのである。
今から10年ほど前、私がAと短い議論をしたときに、「公的な形式なんて、そんなゴマカシはできねえよ」と言ったのは、おそらく、この、暴力と「公的なもの」の秘密を、ぼんやりと感じとっていたからだろう。私は、私党の暴力よりも、公的な形式を備えた組織の方を、怖れたのだ。
* * *
さて。
ここからは、私党の話をしよう。
海賊について。
私たちが海賊というとき、それは古代や中世の海賊ではなくて、主に近代の海賊である。ディズニー映画などの題材にもなっている“カリブの海賊”である。
一般的に、カリブ海賊について社会史研究者が注目するのは、そこにあらわれた階級的性格である。カリブ海賊史とは、簡単に言えば、外洋を舞台にした階級闘争史である。そしてここに加えて私が見ようとしたのは、近代的な啓蒙主義思想をベースにした私党のありかたである。私党はどのようにあるべきかというモデルを、カリブ海賊に求めたわけだ。
法治主義ではない環境において、私党集団はある種の水平主義を実現する。それは暴力の均衡によってである。
海賊船の船長はおそろしく横暴で、暴虐さ残忍さにおいて抜きんでていなくてはならない。その暴力によって船員を統率しているのである。ちょっと機嫌が悪いというだけの理由で、水夫を殴ったり蹴り飛ばしたりする。そういうことが自然にできなくては、海賊船の船長はつとまらない。しかし、殴り過ぎてはいけない。あまりしつこく殴っていると、恨みを買い、復讐されてしまうからである。海賊船の水夫たちは、船長に負けないぐらいの無法者であるから、あまり横暴がすぎると寝首をかかれることになる。この暴力の均衡が、海賊集団の秩序である。
船長の暴力は、無法で理不尽なものだが、それははっきりと船長の人格に帰すことのできる暴力である。ここでは、暴力と人格は一体であって、船長が自らの横暴について責任逃れの屁理屈を並べることはできないのである。
海賊行為が成功して獲物を山分けする場合、船長は水夫よりも多くの報酬を受け取ることができる。しかし、それほど多くはない。史料によると、水夫の取り分が1として、船長の取り分は2~2.5である。現代的に言うと「労働分配率」という言い方になるが、カリブの海賊団の労働分配率は驚くほど高い。船長と水夫とでは取り分は違うが、その格差は意外に小さいのである。なぜなら、もしも船長が欲を出して多くを取り過ぎた場合、それは暗殺と船長交代劇につながってしまうからである。ここでも暴力の均衡が、海賊団の秩序を支えているのである。法治主義でない社会空間において、秩序の要となるのは、暴力の均衡である。
こうした世界では、暴力はすべて私的なものであって、「公的なもの」という想念は存在しない。各人の行使する暴力は、正当なものも不当なものもあるが、それらはどれもはっきりと私人の人格に結び付けて認識されるのである。
地中海海賊からカリブ海賊にかけて、近代の黎明期にあった海賊団は、暴力が充満する空間のなかで、ある種の水平的秩序を生み出していく。アメリカの歴史家ピーター・ランボーン・ウィルソンによれば、この近代海賊団の秩序のなかから、民主政の思想の原基形態が生まれる。民主政は、共和政という思想とは異なる起源をもっていて、別の系譜にある思想である。現代では民主政と共和政は混合しているが、本来この二つはまったく違うものだ。それは現代の我々の態度にも表れていて、たとえば、「公共」や「公正」という概念を疑わしいものと感じる感性のなかに、民主主義思想の伝統が反映しているのである。
* * *
「公的なもの」という想念について、そして、「公的」なものに抗う私党の思想について、述べてきた。
ここからが本題だ。
ある団体で、「組織の私物化」が問題になる。ひとりの中心的な人物が、自分の裁量で「組織を私物化した」というのだ。
私に言わせれば、私物化もなにも、組織とはほんらい私党だ。
組織がまとう公的な体裁は、あくまで便宜的なものであって、そんな便宜的な形式が遵守されようがされまいが、本質的な問題ではない。「組織の私物化」などという問題設定は、そもそも間違っているし、アプローチの仕方としてぬるいのである。そんな立て方では、問題の本質に迫ることはできない。
問題は、人格なのである。
暴力、あるいは支配とは、個別具体性をもった人間が個別具体性をもった人間に行使するものだ。その人格の審級において問い、闘わなければ、問題の核心に迫ることはできない。
相手は「組織の私物化」を遂行できるような人間である。知恵も度胸もあるのだ。もしも「公的なもの」の平面で争うのなら、彼は誰よりも整合的で矛盾なく一貫性のある理屈を述べたてるだろう。そんなやり方で、勝てるだろうか? もしも勝てたとして、そんな勝ちに意義はあるのか? 「公的なもの」の平面で争うなんてことは、まったくバカバカしい。そういう闘い方は、追及する側にとっても、追及される側にとっても、よろしくない。生産的でない。争うべきは、個別具体的な人間の、人格である。
なに? 人格攻撃はよくない? 誰からそんなことを教わったのだ。アナキストの教科書にそんなことは書いていない。人格攻撃おおいにけっこう。ただし陰口ではなく、正面から、公然と、人格をかけて闘うべきだ。
おれはおめえがきにくわねえ、まずはそれだけを言えばよい。
そうして公然と、正面から、人格をかけて闘うのなら、その先には、嘘のない本当の関係がつくられるだろう。